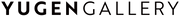見慣れた風景をずらす
ふくよかな筆触と絵具の触知感が絵画の質量を感じさせ、画面いっぱいに原色が散りばめられ描かれる花。自然物の生気に溢れながら、画面はデジタルで起こるバグのように歪んでいる。均衡のとれた絵画世界を構築しながら多層的な画面を展開する、witness(ウィットネス)。
本展では、作家が近所の小道や公園などで目にした草花や風景、花瓶に生けた植物を記録し再構築したペインティングを約20点公開します。
witnessは、福岡県出身。サッポロビール、スターバックスといった企業のビジュアルを手がけるグラフィックデザイナーであり、アーティスト。友人に誘われライブペインティングを行ったことをきっかけに本格的に絵を描き始め、20年以上にわたり活動しています。
「単純に視覚効果として面白いと思ったのとフォトショップといったグラフィックソフトのようなカット&ペーストがアナログでできる」ことに気づき、マスキングテープを使ったアクリル画に取り組んでいます。キャンバスにマスキングテープを貼り、色を塗った後にテープを自由に貼り替えて画面を分割、再構成しキュビスム的視覚効果を演出します。
この手法によって示されるのは意識や記憶のズレ。私たちの見ている風景や事物はひとつではなく、多様かつ並行して存在する。日常の一瞬には、さまざまな時間や記憶のレイヤーが積み重なっていることを表現しています。
人間が心情を投影する花
「見慣れてる風景を一行だけずらす」。日常で見慣れているだけに気づいていない幸せがあるのではないか。それらを丁寧に見つめ拾い上げ、見ているようで見ていなかったもの、思いもよらなかったものを組み合わせることで絶景に出会える、とwitnessは話します。
こうした気づきを得るきっかけになったのが、部屋に生けた花でした。それまで花には全く興味がなかったものの、日々刻々と色、かたちを変えゆく姿に惹きつけられ、「人は自分自身の存在を花に投影している」ことを感受。10年ほど前から主なモチーフとして花を描くようになりました。
時に可憐に、時に周囲を圧倒するほどの鮮やかな色を放つ。盛りは過ぎ、しおれ、落ちていく。花のうつろいに心情を重ね合わせることは誰もが共感するところです。そして、その情景の記憶に生まれるズレ。私たちが現実として捉えるものは固定色をもたず、時間や空間は歪み、記憶と存在は曖昧になっていくことが描き出されています。
日常に潜む神秘を呼び起こす
「写実ではない」としつつも花の形態をしっかりと捉え再構成するwitnessの画面は、絵画とは順序立てて集められた色彩の集合であり、絵具が集積した構造物であることを強く印象づけます。また、図と地に鮮やかに濃く塗られた色はそれぞれが自律的ニュアンスを帯び、色自体の存在を証明するかのよう。
その賦彩からは絵画における図と地の探究心がうかがえ、マスキングテープを使った工学的構成に大工だった祖父の影響からくる建築への関心、そしてグラフィックデザイナーの背景も見てとることができます。
「これまでマスキングテープを使ってきたのは正しく像を結んでいないいびつさや不完全さを受け入れ、ズレを楽しんでいたところがあります。でも、今は自分の目で見たものをきちんと捉えたい」
近年「絵画と向き合う」意識が芽生えているといい、マスキングテープを使わずオーセンティックな絵画作品に注力するwitness。物の名称や意味が揺らぎ、意識がズレる。そうした神秘は必ずや日常に潜んでいる。膨大なイメージが溢れる時代にあって、身近なものを自分の目できちんと見つめ、手元の神秘を呼び起こす。絵画の本質であり、ささやかで最大の幸福を追求しています。