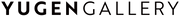図工室に居残る幽霊
透明感がありながら奥行きのある色面。幾何学的形象がリズミカルに配置され、ドローイングがシャープに浮かび上がる。描かれた風景は砂漠地帯のような乾いた空気感を保ち、コミカルなキャラクターはクール。しかし、画面から人肌のぬくもりを感じさせる秋元机の作品。
本展はペインティングとコラージュを組み合わせ、平面や半立体作品を制作してきた秋元が創作の原点である「図工」に立ち返り、新たなアプローチを試みます。あらためて「表現とは何か」を自身に問いかけ取り組んだ作品15点を公開します。
秋元机は2012年、ほぼ日刊イトイ新聞「第二回ほぼ日マンガ大賞」を受賞しマンガ家、イラストレーターとしてキャリアをスタート。アートフェア「UNKNOWN ASIA」(2017年)をきっかけにアーティストとしての評価を獲得し、国内のみならず韓国、中国、台湾等で個展を精力的に開催。海外のアートフェアにも多数招聘されています。
タイトルにある“Art Room”は図工室、“Ghost”はそこに取り残された作家自身を指しています。子どもの頃に夢中で手を動かし、ものを作っていた図工室──そこにまだ居残っている感覚。「図工室の幽霊」とは、社会の枠組みやアートという制度の外で、“つくる”ことに誠実であろうとする存在を表しています。
距離と時間を作る
「『アート』に取り組むうちに、いつの間にかぎごちない表現になっていた。ギャラリーやアートフェアで作品を発表し活動してきて画家のようにふるまってはいるが、作るものは小学生の頃とさほど変わらない。今だに小学校の図工室にひとりでいるような気がする。友だちは卒業し、先生も退職し、学校も廃校になったことに気づかずに、鉛筆やクレヨンで絵を描き、空箱や空き缶で立体を作っている。いまだに真っ暗な校舎にいる自分は、なんだか幽霊のようだ。この気分はネガティブなものではなく、ものを作る原点に立ち返る感覚である」
秋元がこうした意識をもつようになったきっかけのひとつは、昨年参加した中国・深圳で開催されたアートフェア。日本からともに参加した旧知の作家が主催者側の検閲により作品の一部が展示不可に。秋元自身は検閲を回避したものの、規制に則る自身の表現が保守的なものに感じたといいます。
そこからキャンバスやアクリル絵具以前、子どもの頃に慣れ親しんだ画材を使い、原初的で新しい表現を探ります。着目したのは「鉛筆と印刷の中間にあるような曖昧な質感が気に入っている」というカーボン紙。事務書類や伝票など長らく用いられているものの、使用機会は減っている素材を使った新作はドローイング作品とも違った趣向があり見所です。
カーボン紙に引かれた線は遠く、昔からそこにあったよう。さらにエイジングやダメージ加工を施し、描くという身体行為の痕跡に時間の経過が表出し、描かれるモチーフは架空の世界の現象のようで現実と隔絶した距離を感じさせます。秋元が画面に立ち上がらせるのは「距離」と「時間」の概念。
豊かな孤独を携える
コラージュで多く用いる海外の古雑誌。それを手に入れるために通い詰める古本屋や骨董市を「距離と時間を濃密に感じさせるものが多く存在し、自分の発想に欠かせない場」と話す秋元は「距離」と「時間」に関心を寄せてきました。
距離と時間は人間が克服したいテーマであり、テクノロジーによって至るところで解消されてきているもの。遠くの場所にいながらもつながることができ、時間対効果は向上しています。世界から届くメッセージには反射的に反応。金融取引システムは国境や時間をまたいで駆動している。そのようにあらゆる距離と時間を埋めていく一方で私たちは「豊かな孤独」を手放してしまっているのではないか。秋元が作品に潜ませる「距離」と「時間」にそんな問いかけを読み取ることができます。
「頼まれてもなく、必要でもないものを作るというのは妙な行為だと思う。まして時間と労力をかけるのは冗談のようにしか思えない」
ハンナ・アーレントは「孤独」と「孤立」は分けるべきだと言っています。孤立は他者といても心はつながらず親しくできず、かつ自分らしくもいられない寂しい状態のこと。一方、孤独は本来の自分自身と時間をかけての対話があるもの。それは自由で豊かなこと。秋元のいう冗談のような無駄ー芸術、映画、音楽、文学等々ーに保たれる距離と時間を前に私たちは豊かな孤独を手にしています。
タイムラグがない時代に生きることになった私たちは寂しさを断続的にまぎらわし、とうに孤独を置き去りにしてしまっているのではないか。図工室に、豊かで孤独な幽霊が現れます。