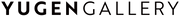人気絵本作家の知られざる世界観
『給食番長』をはじめとする学校シリーズなどロングセラー絵本を多数発表し続ける、よしながこうたくは1979年
福岡県出身。自由奔放なキャラクターを絵具だけで力強く描き上げるタッチと映像のカメラワークのような画面構成、そして博多弁を併記した「博多弁バイリンガル絵本」なる様式を特徴とし、全国各地で行われる本人による読み聞かせ、子ども達と一緒に絵を描くライブペインティングはこれまでに300回以上行われるなど絶大な人気を誇っています。
そんな人気絶頂の絵本作家の知られざる世界観を初公開するのが本展「三途の川の此岸路」。欲や煩悩から解放されたあの世を指す彼岸。そして苦悩に満ちた人間世界の此岸。三途の川を渡ることなく此岸の波打ち際に寄せて溜まるもの。それを此岸沿いを歩きながら眺めるイメージをもって、よしながはキャンバスに向き合います。
見えない世界への想像
このテーマは九州北部の豪雨水害の被災地を見に行ったことがきっかけになっています。災害の大きさを物語る爪痕を残しながらも、神々しい美しさを讃えていた川。そこに浮かぶ流木と思しきものが、川に沈む鹿の角だったこと。鹿の屍と目があった時、生と死が一気に倒錯します。死屍に見つめられ、流れ出した岩だと思っていたものは鹿の頭であり、自分の足元の水溜りらしきものが血溜まりであることに気づきます。それまで輝かしく生命に溢れていた場所が死の世界へと転覆され、その時に三途の川の畔というテーマが浮かび上がってきました。生者が見つめる死の世界から、死者が現世を見つめ返す感覚が去来します。
よしながの異界感覚とも呼べるものは、8歳まで過ごした築100年の家での暮らしが影響していると話します。「食事の準備中、目を離している隙に卓に並べていた夕食をイタチが食い尽くしてしまったり、家に置かれた害虫駆除用品にはネズミが列になって捕まっているのも当たり前。古くてボロくて、広い家の薄暗い渡り廊下の奥に祖父母の部屋と仏間があり、そこで毎朝お経を詠まされた」。
浄土真宗の寺に生まれた祖母の教えや、家の中で野生動物に境界が破られる感覚。生活する空間に隣り合わせる死など目に見えない世界への気配は福岡小倉という海の街の湿気とともに、よしながに染み込んでいきました。
また南米の移民研究に携わっていた父親に連れられ、小学生の頃から南米中を巡ったというよしなが。父親が基金を募って現地に小学校を建設していたことから
アンデス山脈の小学校に同行した際、小さな女の子と握手した時の手の感触は今でも覚えていると話します。ゴツゴツとした、農作業や家の仕事を手伝って働いている人の手。バラックのような家が並ぶ集落など自分が生きている世界の裏側に想像を超えた暮らしがあることを目の当たりにします。
「高校生の頃シャーマンの元で絵を習っている子ども達に会うと、自分が当時通っていた学校のデザイン科の誰よりも絵がうまかった。その子たちが“いつか日本に行ってみたい”と目を輝かせて言うのだけど、それは一生叶わないのではないかとも思った」
帰国してから、周囲の友達にそれらの体験を話しても誰にも理解されず、「いろんな土地で、いろんな人が同じ時間の中で生活をしているけれど、それらが交わることが無い」とぼんやりと学生生活を送るだけの日々に諦念めいたものが打ち込まれました。
日々を祀る「毎日御神体シリーズ」
コロナ禍で誰とも会うことなく「一日一日がずるずると流れ去っていく」なかで、そのようなかけがえのない日々への感覚が迫り、生まれたのが昨日と今日、そして明日といった毎日を御神体に見立て絵日記のように描いた「毎日御神体シリーズ」。
これは、絵本作家の活動を休止した2017年以降にアジアの国々を旅するなか、どんな屋台の端にもお供え物があるなど生活に宗教が根付いていることを感じ取り、日々を御神体と見立て365日365体祀ることを思いついたもの。これまでの絵本のストーリーを伝える絵から、その日一日のストーリーの象徴、観念の具象として御神体を描きます。
2017年に行われた福岡の老舗ギャラリー《アートスペース貘》での二人展「命のありか」で久しぶりにキャンバス作品に取り組み、目に見えている「この世」と、人間による意味づけを超越した「あの世」をテーマとし、これまでの絵本作品からは想像が追いつかない世界観を表し話題となりました。本展では、それらの平面作品に大幅加筆。新たに取り組んだ御神体シリーズの他、かけがえのない一日からたどり着いた三途川の畔をテーマにした小作品『夜流小唄(よながしこうた)シリーズ』も加え約30点を初公開します。
今を生きる喜びを彼岸へ届ける
行動が制限され、絵に向き合うだけのこの数年で、よしながは父や知人を亡くします。それもまた去りゆく日々を強く意識づけたのでした。人生において死に怯え続けてきたというよしながは、誰にも死が訪れることを特に父親によって見せられたことで「悪夢のように消えなかった」恐怖が消え、生の喜びから死を見つめることができるようになったと話します。
これまで行なってきたライブペインティングでは、思いもよらない箇所に筆を入れる子どもたちに「自分の絵を壊せるようになり、固まっていた思考や筆運びをほぐしてもらった」と話します。2002年イラストレーターとして出発するも、独特のタッチがどこにも受け入れられず、よるべない日々を過ごし絵の道は断念せねばならないだろうと思っていた矢先に、偶然、絵本の道が開かれたよしなが。自分の絵を唯一認めてくれた子ども達ーそれはかつて南米で出会った“交わりえない”子ども達とも重なるーへの忠誠を誓うように絵本作家として邁進してきました。
よしながの此岸はこれからも絵本であり続けますが、「自分の核となる絵の追求」も此岸の波打ち際に留まっていては三途の川は渡ることはできないとし、「自分の走馬灯を充実させる準備作業」として、一日一日生きる喜びを祀り上げるものとして絵と向き合います。
幼少期から死の偶然性と隣り合わせることを知覚し、鹿の死屍との遭遇により生と死の接続を直観したよしなが。不安に晒される日常で一日一日ここに生きる喜びを願う「日願」とは、彼岸という享楽への祈願として示されるのです。