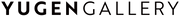芸術作品はルールを作るが、ルールは芸術作品を作らない。
クロード・ドビュッシー
鏡をもつ者の写真が入った小さな器、そして一輪の青い薔薇。密集して並べられ、合わせ鏡のようにしてイメージは無限に繰り返され拡張していく。廃墟に横たわる女性の裸体、そして遠い記憶のように女がひとり映るセピア調の写真作品。写真家・堀清英による銀塩とデジタル出力の写真作品約30点をはじめ、モノと写真をコラージュするように制作した立体作品で構成する展覧会。
「Free again」とは、アレックス・チルトンの同名曲から取られたもの。「歌詞にあるsheの部分を自分自身が経験したある言葉に変えてみると、自分の気持ちに当てはまった。インターネットをはじめとするバーチャルなクロスカルチャー、情報の質や価値観の変化などを受けてアメリカと日本でのふたつの写真のお作法とは、そろそろお別れの時期」と語り、固定観念や人間関係、そして自分を縛り付けていた自意識を下ろし写真家として新たなルールを手繰り寄せる芸術への意思を感じます。
連鎖反応から生まれる作品
堀清英は1991年に渡米。ニューヨークのICP(国際写真センター)で写真を学んだ後、写真家として活動を開始します。自身が影響を受けた詩人のアレン・ギンズバーグやデニス・ホッパー、ロバート・デニーロ、オノ・ヨーコといった歴史的なアーティスト達のポートレートで知られるようになり、’97年日本に帰国後は、ファッションや音楽を中心に人物撮影を数多く手がけています。
近年は「自分とは何者か?」をテーマにした作品制作に注力。東日本大震災後に取り組んだ現代社会へのアイロニーを示すシリーズ「re;HOWL」、シュルレアリスムの影響を強く感じる作品群で複層的に構成された展覧会「RED」といったナラティブな作品を発表しています。
堀が、写真よりも好きなことと話すのが「モノを分解すること」。偶然見つけた工業製品や家財道具、風化した廃材を拾ってきては分解しモノと繋ぎ、写真と組み合わせる。「誰に見せるわけでもなく、何ものにも囚われず」日々創作してきた作品も公開します。
堀が写真家を志すきっかけになったのは20世紀有数の肖像写真家のユサフ・カーシュ。堀自身も彼にポートレートを撮影してもらった経験があるほど私淑しましたが、目指したのは別の道でした。
「カーシュが生涯やり続けたのは会話を通じてカーシュ調といえる表情を被写体から引き出し、その人の魂の輝きを荘厳なライティングで表現すること。それは、自分には向いてないと思った。ロードムービーのように移動するなかで出会った街で自分の気持ちと交換できるものを感じ取り、撮影するやり方に気づいた。ストーリーを作るのではなく動きながら人、風景に反応して作品を生み出す。そこで生み出した作品に反応して、また作る」
撮影と分解による同期と非同期を繰り返し、反応の連鎖を止めずに生み出されるイメージ。2022年シャネル・ネクサス・ホール での展覧会「RED」で「鏡というシンボリックなものが制作の旅に連れて行ってくれた」と話すように、堀はモノや風景が発する声を聞き取り、現代の生活でかき消されつつある人間の感情のメタファーを示します。
迷い込んだ先にある予感
1976年に発表された写真家・中平卓馬の《デカラージュ》を想起させるような表情の違う白壁を捉えた写真7枚組み作品《#8157》では、堀はバッハのゴルトベルク変奏曲を口ずさみながら撮影していたと話します。変奏曲の多くは曲頭でテーマが明確に提示され、そこから聴き手は変奏を追いかけることになりますが、ゴルトベルク変奏曲は冒頭から聴き手を道に迷わせます。架空の世界の落とし物のような堀の作品群も変奏を重ね、観る者を迷い道へ誘い込む感覚があります。
「自分の奥に仕舞い込んでいたものを解放する。自分の中のよろしくない感情でさえも何かの予感になっていて、それを見てやろうという気持ちになっている。その予感は動かさないといけない」
撮影した風景を刺繍で表し、その裏面はPCのバグのよう。一筋縄でいかない堀清英の作品に漂う不安と予感の変奏。それは、音符が極限的に増殖しても均衡美を崩さず、ついにはユートピアを現したともいわれるゴルトベルク変奏曲のように論理では体感できない知覚の変化を引き起こすことでしょう。