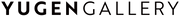幻想的なアンソロジアンの肖像
動物の骨のような形の何かが割れた破片。それらを組み合わせると哀愁漂う肖像画のような絵画が現れる。海辺に漂着した小さなプラスチック片から想像し、詩的な表現を試みるステンシル・アーティスト、赤池完介による展覧会「ANTHOLOGIAN」。
これは“anthology”と“humanity”を組み合わせた赤池による造語。神奈川県湘南地域に住む赤池は、日頃海岸でゴミ拾いをしており、それを「広い海辺で輝く個性に瞬間的に反応し、花を摘むような行為」であると話します。アンソロジーの語源であるanthologiaには元来「花摘み」「花集め」の意味があることから着想し名付けたシリーズ約20点を公開します。
「役目を終え捨てられ、長い時間をかけて劣化し形を変えたプラスチック片。どうしようもないものたちに詩的な魅力を感じた。いびつながらもストーリーを抱え、再び命を与えられて歩むアンソロジアン達の幻想的なポートレート」
1974年京都生まれ。仏師の仕事をしていた父親と鞄作りに携わっていた母親の影響から幼少期より手仕事に親しみ、京都にある文化遺産が身近だったことから美術を志します。思春期にパンクロックの既成概念を壊していく姿勢に魅了され、伝統的な芸術へのカウンターカルチャーであるポップアートを志向します。
アンディ・ウォーホルやジェイミー・リードらの作品に感化され、進学した武蔵野美術大学では専攻とは別にシルクスクリーンやコラージュによる作品を独自に制作していました。それまで制作拠点としていたシルクスクリーン設備が使えなくなったことをきっかけに「仕方なく」選んだ方法がステンシル。赤池が「見つけてしまった」というように自身にとっての真の芸術の原石を見つけ、一枚の作品をステンシル技法のみで仕上げる現在のスタイルへと磨き上げてきました。
即興性を排したステンシルの絵画性
以来、パンクやストリートカルチャーのDIY精神を原動力に衝動的なコラージュを主なスタイルとし、国内外での個展やグループ展、広告やナショナルブランドとのコラボレーションワークを多数手がけてきました。しかし、近年は海や山に囲まれ、ゆったりとした時間を過ごすうちに、ひとつひとつじっくり時間をかけて日常を観察しインスピレーションを得るようになります。
「以前、南伊豆に住んでいた時に風景の色々が綺麗に見えて、モチーフが新鮮なものになっていった。最初から絵にしようとして見るのではなくて、ただ綺麗だなと感じたことを素直に表現してみたいと思うようになった」
そこからステンシル技法の特徴である即興性や反復性を極力抑え、スプレーペイントによるタブロー(絵画)表現を試みる意識が芽生え、生まれたのが今回発表する〈アンソロジアン〉。これはサーフィンの帰りに始めたごみ拾いがきっかけでした。
「海から上がってサーフボードを担いで帰る時、空いている片手でゴミを拾って帰ろうみたいな暗黙のルールがある。片手だから全部は拾えないのでゴミを選ぶわけだけど、自分が綺麗だと感じたものを拾っていく感覚が面白いと思った」
そうして集めたものを家に持ち帰って眺めるうちに、どれもが愛おしい存在に感じられたと話します。ドローイングし並べて、組み合わせると抽象的な絵になる。赤池自身にとって新しい境地となる予感がありました。
再生社会の先にある、シュールな未来
「こうしていびつな形になったものを見ると、どれだけの時間が流れ、こんな風になっちゃったんだろう?と思う。現代生活のスピードに合わせて無理矢理生み出されたものが、つまはじきにされてしまったところに奇妙さや哀愁を感じる」
「シルクスクリーンにしてもステンシルにしても版ズレとか、そこから生まれるエラーが面白い。偶然性の美しさ、常識外として人が除外していくものに魅了される」
物質から滲む人間性、情感が現れる陰影のつけ方など画面から感じられる崇高な印象は、19世紀フランスを中心に興った写実主義、特に貧しい農民を描いたジャン=フランソワ・ミレー作品に通じる雰囲気を感じさせ、反復と即興の芸術であるステンシル・アートを永続的な絵画たらしめようとする赤池の目論見が果たされているといえるでしょう。
海辺のゴミは「現代人のぼやき」といい、そこに感じとるSDGsや再生社会といった社会に喧伝される正義の嘘っぽさや常識とされるものから外れてもがく人々の哀愁を、写真や絵画で残る肖像画に特有の滑稽さをもって描くアンソロジアン。本展では作品のモチーフとなったゴミ、それを写し取ったデッサンも展示します。
社会のシステムや文脈をジャックし価値観をずらして見せるストリートアートの手法で浮かび上がらせるのは、“再生社会”の先にあるシュールな未来像。それは、ステンシル・アートの可能性を信じる赤池による写実なのです。