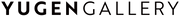初めて取り組んだ油彩画
クリエイティブユニットのエンライトメント所属アーティスト、中島友太。2020年から本格的にアーティストとして活動を始め、戦後から1980年代にかけてのカルチャーをモチーフにエロ・グロ・ナンセンス感覚に溢れるコラージュ作品を制作してきました。
大阪府出身の中島は「横文字の職業がカッコイイ」との理由でデザイナーを目指し、デザイン専門学校卒業後に上京。グラフィックデザイナーとしてキャリアをスタートし、広告などを中心に活躍しています。コマーシャルワークの一方でグループ展や企画展へ精力的に参加し、2021年コンテスト形式のアートフェア「UNKNOWN ASIA 2021」では審査員賞・徳光健治賞を受賞しています。
本展「TRANSFER」はデジタルコラージュを主な手法としてきた中島が作風を一転させ、近年取り組み始めた油彩画のみで構成。本展のために描き下ろした新作7点を含む9点を公開します。
誰もがどこかで見たことがあり、懐かしい。しかし、何もかもが“ファスト”な現在においてスキップされてしまう古い映画の1シーン。それらをインターネットなどから集め、原初的なメディウムであるキャンバス上の油彩画に置き換えて新たな心象風景として描き出します。
「昔の白黒映画やビデオの中から琴線に触れたオブジェクトやシーンをセレクトし、データを別の場所に移し替える(トランスファー)と摩擦が起こる。それは時空の歪みのようなもの」
デジタル上で下絵を作った後にキャンバスに落とし込み、油彩絵具で色を重ねていく。登場人物や風景の輪郭をぼかし、既視感のある眺めを変容させる中島の作品はイギリスの画家、ピーター・ドイグを想起させます。
人間のわからなさを描く
これまで自身で撮影した写真や古本のスキャン、SNSで集めた画像などをデジタル上でコラージュ。その上にアクリル絵具で彩色した作品を発表してきた中島。猥雑なモチーフを節操なく集め構成される画面からはグラフィックデザイナーとしての論理性とそれを台無しにしてしまうかの激情が入り交じります。そこに浮かび上がってくるのは人間の業といえるもの。
今年30歳になる中島は、ひとりの歌手が歌うのをテレビの前で国民全員が聴き入るような昭和の価値観に憧れがあるといいます。保育園への行き帰りの車の中でいつも聴いていた美空ひばりやグループサウンズといった音楽、全50作品すべてを観ている『男はつらいよ』などの映画。特に好きだという向田邦子脚本のドラマ『阿修羅のごとく』では、人間の喜怒哀楽それぞれの裏にまったく別ものの収拾のつかない感情がうごめいていることが描かれ、強く惹かれると話します。
絶望的な悲しみが喜劇のように映るのも人間の性。「なんの目的意識もなく面白そうだと思うイメージを集めて繋ぎ合わせていくうちに思いもよらない絵となる」と話す中島のコラージュは、人間がコントロールのきかない“わからなさ”で行動していることの表れであるといえます。
平凡な瞬間に現れる「業」
コラージュにせよ、そして今回取り組んだ油彩画にせよ中島は最終的なイメージを思い描かず、「無意識を意識して」手を動かしているといいます。ましてや社会的メッセージを含ませることもありません。
「具体的に描こうとすると、その目的にのみ向かってしまう。感覚のままに制作していき作風も固めず作品を作っていきたい。スタイルを決めたとしても変わっていくし、それでこそ作品は生き続けると思っている」
デジタルコラージュから油彩へと手法を変えたのはデジタルにはない油彩絵具の色、匂い、手の汚れといった生身の五感を求めてのこと。創作とは「自意識への抗い」であり、合目的のみで生きていない人間の証明なのです。
「SNSでは数秒で情報が入れ替わり、日常生活では新しい情報をいつも捨てているような状況。便利なのは間違いないけれど個々がどんどん軽く扱われていることに抵抗したい」
映画においては1秒足らずで過ぎ去る瞬間。人生で幾度となく目にしているシーン。中島によって抽象化された絵画に鑑賞者はそれぞれが経験や記憶を上塗りし、想像の領域が広がることを感じ取るでしょう。そして誰にも覚えのある、ごくごく平凡な瞬間に人間の業という永遠が潜むことも。
「人間ばかり描いているので、バランスを取ろうと思っただけ。あまり意味はない」として一軒家を描いた作品〈Orange roof〉。人の気配はないものの、確かに人の生活と地続きになっていることを思わせる。続々と新しい表現技術が生まれるなかで時代遅れともいえる絵画で人間の景色を描く。中島の作家としての業は確かに現れています。