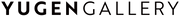抽象と具象の間にあるもの
異国の友人から届いた手紙のような感触。そこに描かれるのはシュールな世界。秋元机は、ほぼ日刊イトイ新聞の「 第二回ほぼ日マンガ大賞」グランプリ受賞(2012年)をきっかけにキャリアをスタートし、書籍やTVCMのイラストなどを手がけています。
古本屋や蚤の市で見つける海外の印刷物に題材を取るコラージュとアクリル絵具によるペインティングを組み合わせた手法で平面作品のみならず立体作品も制作。個展やグループ展、アジアのアートフェアに招聘されるなど国内外で人気を博しています。
ひとコマ漫画のような具象作品やコラージュによる抽象絵画を描いている秋元。作風を固定するのではなく具象と抽象の間に漂うものを描くことに関心があると話します。テーマに囚われることなく色、形、そしてアクリル絵具など画材のテクスチャーに集中し描いたペインティングとコラージュ作品で構成する「抽象と具象と社長」。新旧作品を約20点公開します。
「意味やコンセプトは二の次という姿勢で絵に取り組んでいると、自分が求める絵は、抽象と具象の間にあると感じる。タイトルはずいぶん前に思いついたフレーズで、語感が気に入っていた。社長の意味するものは何なのかはわからないけど、たぶん抽象でも具象でもないところでのえらい立場なのが社長なのだろう。社長がどんなものなのかしばらく追い求めてみたい」
気持ちの良い“気持ち悪さ”
元来文章を書くのが好きだったことから大学では文学を専攻していた秋元。卒業後は、映画学校で学び、自主映画や商業演劇の制作に携わっていました。秋元の手跡や色数の多くない画面からストーリー性が感じられる理由はそこにあるといえるでしょう。
色遣いにしても気持ちの良い組み合わせだけでは心に引っかからないという秋元。「気持ちの良い気持ち悪さ」、ノイズをテーマに見慣れた日常に異物が混在する世界を描きます。
「他の作家の作品にしてもわからなすぎる、自分の好みではない表現に対して興味が湧いています。それは、理解しかねる不快感ではなく魅力的な謎。作り手としても自分が描きそうにない絵、作りそうにない表現が遠い理想としてある」
工具の図版など「自分の関心領域外」の素材をサンプリングし編集することから「自分の想像外」の創造物が生まれるコラージュ。魅力的な謎を追求する手法としてコラージュをベースに、アクリル絵具でペインティングを施す手法で作品を制作してきました。
自身も思いもよらなかった表現に遭遇する面白みのいっぽうで、美術の専門教育を受けていない引け目からペインティングに向き合うことが出来なかったことの葛藤もあったという秋元。そこから「ストレートに気持ちを腕に乗せ、色と形の魅力にいちばんの重きを置いた」絵を描きたいと強く思うようになり、純粋なタブロー表現を求めてキャンバスに向き合い、本展ではペインティング作品に取り組んだ作品も発表します。
「今、スマホでいろいろなものを見ていても全部均等の大きさに思ってしまうけれど、実際に見に行けば想像よりも大きかったり小さかったりする。見る側の勝手な想像とは違うものを前にした時の気持ちの悪さやおかしみこそが心に残る」
例えば広大な風景を5cm角のキャンバスに描くといった試みに観る者の感覚を揺さぶる意図が見てとれ、鑑賞者は身体の奥底に潜む音に聞き耳を立てるように感覚が開かれるのを感じられるでしょう。
不確かで不安な私たち
実はモチーフにそれほど関心がなく、絵を描いている時は色遣いやテクスチャーのみに反応しているという秋元。美術やアートで用いられる「抽象」や「具象」といった言葉もどこか古びていて、現在は有効ではないと感じ、その間の揺れ幅みたいなものを表現したいと話します。
それはデジタル以前、周波数の合わないラジオのチャンネルを探すようなものであり、誰もが知ってはいるもののその実在はモヤモヤしている「社長」がコンセプトに浮かび上がってきました。
秋元は、コラージュせよ思うままにキャンバスに色を塗るにせよ、何が出来上がるのか自分でもわからない不安な過程から作品と呼べるものにたどり着きたいと話します。そこで生まれるものは「ひとコマ漫画の一歩手前のようなもの」とも。
生きる本質とは気持ちの良い気持ち悪さにある。不安な過程から生まれる秋元の作品に、不確かで不安な存在の私たちを見つけるのです。